今日は8月6日。
日本人にとって忘れられない日だ。
そう、今から80年前の今日、広島に原子爆弾「リトルボーイ」が投下され、14万人以上(1945年末まで)が亡くなった。
その3日後には、長崎に原子爆弾「ファットマン」が投下される。
約7万4千人の人々が命を失った。
戦争の悲惨さを物語る際に、これほど説得力のある出来事はないだろう。
人間の尊厳さえ奪われてなくなっていった人たちのことを思うと、心が苦しくなる。
広島、長崎の悲劇が閃光と共に一瞬で街を焼き尽くした悲劇だったとすれば、沖縄のそれは、3ヶ月にわたって鉄の暴風が吹き荒れた、終わりの見えない悲劇だった。
僕は沖縄出身で、現在は沖縄で暮らしている。
沖縄もまた、戦争の悲惨さを物語る説得力を持っている。
沖縄では6月23日が「慰霊の日」と定められており、学生や県および各市町村の職員は休みとなっている。
多くの人が、沖縄戦戦没者のために糸満市摩文仁の平和記念公園内にある「平和の礎」に祈りを捧げに行く。
そして、各地に建立された慰霊碑に手を合わせるのだ。
僕自身も平和の礎に行き、祖父や伯父の名前が刻まれた礎の前で手を合わせる。
礎に刻まれた祖父の名を指でなぞるたび、僕は歴史の教科書には載らない、家族の痛みに触れる。
会ったことのない祖父や伯父の生きた証が、冷たい石の上に、確かにあるのだ。
遺骨が納められている「魂魄の塔」へ向かい祈る。
遺骨が納められていると書いてはいるが、実際には「周辺に散乱していた遺骨3万5千余柱(魂魄の塔碑文より)」を納めている慰霊碑だ。
激しい地上戦が行われた沖縄。
どこで亡くなったのかわからない戦没者も多くいる。
その方々の親族は、亡くなった肉親や兄弟がここに眠っていると信じて手を合わせに来る。
誰がどこで亡くなったのか、その遺骨がどこにあるのかさえわからないほどの焼け野原となった沖縄。
沖縄戦では軍人や軍属、一般市民を合わせて20万人を超える人々が亡くなっている。
ちなみに、一般市民の死者は5〜6割を超えるといわれている。
その光景は、誰も想像することができないほどの悲惨なものだったのではないだろうか。
そして、恐ろしいことに、その悲劇を実際に経験した人がいて、まだその痛みを抱えながら生きておられるのだ。
広島や長崎も同じだと思う。
人間が経験したこともない悲劇を経験し、体はもちろん心にも深い傷を負いながら生活しておられるのだ。
戦争を終えるためには仕方なかった。
これ以上、犠牲者を出さないためには、これ以外に方法がなかった。
そんな声も聞こえてくる。
しかし、本当にそうだろうか?
日本はその頃、既に終戦工作を行っていたはずだ。
それなのになぜ、多くの人々が惨たらしい死を迎えなくてはいけなかったのか。
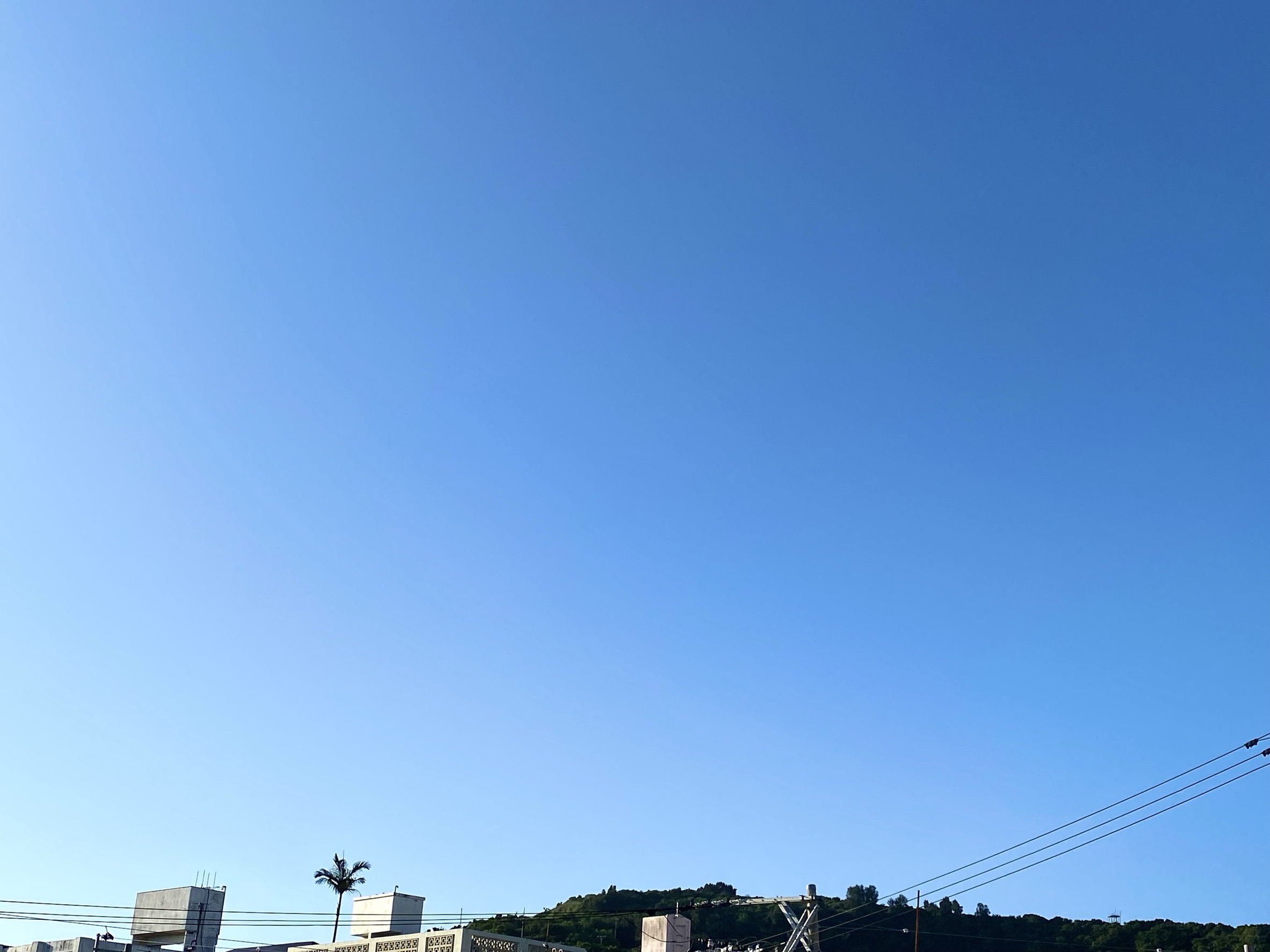
毎年、何度か平和について考える日がある。
その一つが8月6日だ。
ほんの少しで良い。
今日という日は、平和について考えてみよう。
80年前のあの日、広島の上にも、きっと同じように青い空が広がっていたはずだ。
そのあまりにも美しい空の下で、あの悲劇がやって来た。
だからこそ僕たちは、この青空を見上げるたびに、平和の意味を問い続けなければならない。
青い青い空を見上げながら、僕はそう思った。
